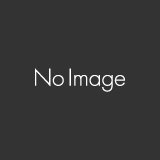【長期投資向け銘柄】オールマイティ銘柄6269 三井海洋開発について
- 2025.10.31
- 投資
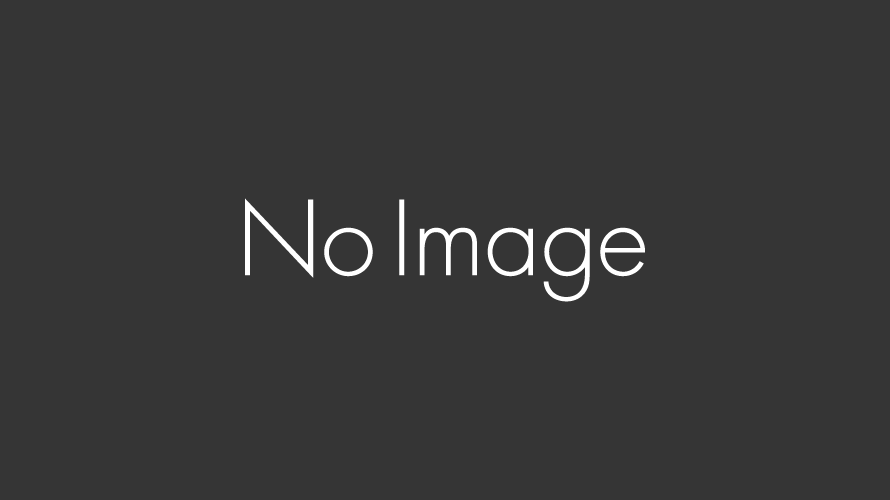
最近、株式市場では「国産レアアース開発」が大きなテーマとなり、東洋エンジニアリング(6330)をはじめとする関連銘柄が高騰しています。
この国家プロジェクトの「海側」を担うと期待される三井海洋開発(6269)も、そのテーマ性で注目を集めています。(6330とPER比で見ると注目度が弱いですが・・・。)
本銘柄は「国産レアアース」というテーマ銘柄の側面もありますが、本質は同社のビジネスモデルそのものの圧倒的構造的強さにあると感じました。
本銘柄を分析する中で感じたのは「安定性(ビジネスモデル)」「将来性(レアアース)」「成長性(FPSO建設)」であり、安定したビジネスモデルの中でも1発を狙える銘柄と感じました。
そう判断した分析を共有します。
安定性について
圧倒的なキャッシュフローを生む「海上工場の大家」
三井海洋開発の売上の作り方は、2つのフェーズに分かれています。
- EPCI(建設)事業: 顧客(石油会社)の注文を受け、FPSO(海に浮かぶ石油・ガス生産工場)を設計・調達・建設し、現地に据え付けます。これは数千億円規模の「単発の建設売上」です。
- チャーター事業(賃貸・操業): ここからが同社のビジネスの核心です。完成したFPSOを顧客に売却するのではなく、自社で保有します。そして、その海上工場を15年〜25年という超長期で顧客に貸し出し、日々の運転管理(オペレーション)まで一括で請け負うのです。
これは、例えるなら「超高性能な海上工場の大家(オーナー)」です。 一度FPSOが稼働を始めれば、原油価格の短期的な変動に関係なく、20年先まで「家賃(チャーター料)」という名の莫大なキャッシュフローが、毎月安定的に入り続けます。
現在、同社は17隻もの海上工場を世界中で稼働させており、この「ストック型」のビジネスモデルこそが、同社の業績の安定性と、将来の安定的な増配を支える最大の源泉となっているのです。
※ビジネスモデル上のリスク
このビジネスモデルの唯一とも言える弱点は、「FPSOの建設」にあります。
FPSOの建造は、数年がかりの超巨大プロジェクトです。もし、予期せぬ技術トラブルや資材の高騰で工期の大幅な遅れ(スケジュール遅延)やコスト超過が発生した場合、そのプロジェクトの利益が吹き飛び、一時的に業績(売上予測)を大きく下振れさせるリスクがあります。
市場が同社に慎重な評価(割安なPER)をつけることがあるのは、主にこのプロジェクト遂行リスクを懸念しているためです。
現在の稼働状況と「確定した未来」
この「家賃収入」がいかに盤石かは、現在の稼働状況を見れば明らかです。
- 現在の安定収益源: 17隻のFPSO/FSOが世界中(主にブラジル沖)で稼働しており、長期契約に基づいた莫大なチャーター料を生み出し続けています。
- 未来の確定した収益源: 現在、過去最大級となる4隻の超大型FPSOを建造中です。これは「受注できると良いな」という期待ではなく、すでに契約が確定している「未来の売上」です。これらが2026年以降に順次稼働すれば、現在の「家賃収入」がさらに上乗せされることがほぼ確定しています。
鉄壁の配当と莫大な「増配余力」
この安定したキャッシュフローは、株主還元(配当)に直結しています。
- 2025年度の配当予想: 1株あたり120円 (これは2024年度の80円から、50%の大幅増配です)
- 予想配当性向: 約19.2% (計算式:
配当120円 ÷ 予想EPS 625.02円)
配当性向19.2%というのは、「稼いだ利益のうち、まだ2割弱しか配当に回していない」ことを意味します。これは、現在の配当が極めて安全であること、そして将来の利益成長に伴い、配当をさらに増やす余力(増配余力)が莫大に残されていることを示す、非常に心強い数字です。
コア事業だけで配当をまかなう「収益力」
この配当が、リスクの高い「建設売上(EPCI)」からではなく、安定した「家賃収入(チャーター事業)」から支払われていることが重要です。
- 2025年度の年間配当総額:
120円/株 × 約5,300万株 (発行済株式数) = **約63.6億円** - 2025年度の純利益予想:
予想EPS 625.02円 × 約5,300万株 = **約331億円**
会社全体の利益(約331億円)は、支払う配当(約63.6億円)の5倍以上もあります。そして、この利益の大部分を生み出しているのが、安定したチャーター事業(オペレーション部門)です。
つまり、リスクの高い建設部門の業績が多少変動したとしても、安定した「家賃収入」だけで、現在の配当は余裕でまかなえる鉄壁の収益構造が確立されているのです。
※チャーター事業だけで本当に配当金を賄えているの?って人向け
通期のセグメント別「利益予測」は公表されていないため、最も確実な最新データである2025年上半期(1月〜6月)の実績で計算します。
- 通期純利益予想: 427億円 (2025年第2四半期決算短信)
家賃収入(チャーター事業)はいくら稼いだか?
決算資料では、リスクの高い「EPCI(建設)」部門と、安定収益の「O&M(操業・保守)+チャーター」部門の利益が明確に分けられています。
2025年上半期(1月〜6月)の実績
- 会社全体の純利益: 229億円(1.45億ドル)
- EPCI(建設)部門の利益: 赤字 (※注:建設部門はコスト超過などで赤字になるリスクが常にある)
- O&M+チャーター部門の利益: 黒字(会社全体の利益を上回る額)
結論:チャーター事業が全ての利益を生んでいる
2025年上半期において、会社全体の利益(229億円)は、すべて安定収益源である「O&M+チャーター事業」が生み出したものであり、リスクの高い「建設事業」はその利益をむしろ少し減らしている、という構図です。
- チャーター事業の安定利益(上半期): 229億円以上
- 年間の配当支払総額: 約63.6億円
安定収益源であるチャーター事業は、半年間の利益だけで、年間に支払う配当総額の3.6倍以上(229 ÷ 63.6 ≒ 3.6)を稼ぎ出している計算になります。
成長性について
市場の寡占と現在の収益基盤
まず、同社が戦うFPSO市場は、数千億円規模の巨額な資金と高度な技術力が求められるため、参入障壁が極めて高いのが特徴です。
競合他社と市場シェア: 実質的に、オランダのSBM Offshore社と三井海洋開発の2社が市場を寡占している「複占」状態です。この強力なポジションが、安定した受注を可能にしています。
- SBM Offshore (オランダ): 約31%
- 三井海洋開発 (日本): 約24%
(※出典:deallabなど業界分析レポートに基づく推計値)
この2社だけで、世界の新規受注の合計約55%を占めています。残りの約45%を、BW OffshoreやBumi Armadaなど、他の多数の企業が分け合っている構図です。
現在の稼働状況: 現在、17隻のFPSO/FSOが主にブラジル沖などの海洋油田で稼働しており、これが前述で述べた安定的なチャーター収益を生み出しています。
※ライバルのSBM Offshoreは、約20隻のリース・操業フリート(船団)を保有しています。
「数」から「規模」へ。FPSOは巨大化している
現在、三井海洋開発が建造中(契約済み)のプロジェクトは4隻と、運用中17隻に対して契約済み件数だけ見ると少なく感じるかもしれません。
しかし、これは「数」ではなく「規模」で見る必要があります。
近年の海洋油田開発は、より深く、より大規模になっており、FPSOもそれに合わせて驚異的に巨大化しています。
- 過去のFPSO: 1日あたり10万〜15万バレルの生産能力が主流。
- 建造中のFPSO: ガイアナ向けの「Uaru」は日量25万バレル、ブラジル向けの「BM-C-33」は日量22万バレルと、過去のFPSOの1.5倍〜2倍近い生産能力を持っています。
つまり、建造中の4隻は、過去の船の6〜7隻分にも匹敵する売上と利益インパクトを持っているのです。1件あたりの売上が飛躍的に増大しているため、数少なく見える受注でも、会社の成長性は極めて高いと言えます。
円安の恩恵と「確定した」建設スケジュール
成長をさらに後押しするのが、為替と明確なスケジュールです。
- ドル建て契約による円安の恩恵: 三井海洋開発の契約は、売上もコストもそのほぼ全てが米ドル建てで行われています。そのため、現在の円安(1ドル約150円など)は、ドル建てで稼いだ利益を円換算する際に、利益の「額」を大きく押し上げる強力な追い風となります。
- 明確な稼働スケジュール: 現在建造中の4隻は、以下のように稼働開始時期がほぼ確定しています。
- 2026年: ガイアナ向け「Uaru」
- 2027年: ブラジル向け「BM-C-33」「P-83」
- 2028年: スリナム向け
これは「〜だったらいいな」という期待ではなく、すでに契約書にサイン済みの「確定した未来の売上」です。
2028年以降の未来:売上倍増と更なる新規契約
- 売上の飛躍的増加: これら超大型の4隻が2028年までにすべて順調に稼働した場合、同社の安定収益源であるチャーター事業の売上高は、現在の2倍近くまで増加すると試算されています。
- 新規契約への期待: これで終わりではありません。ブラジルやガイアナ沖の石油開発ブームは依然として活況であり、三井海洋開発は現在も複数の新規案件の入札に参加しています。今後も年間1〜2隻のペースで新規受注を獲得し続ける可能性は十分にあります。
このように、同社の成長性は、足元の確実な受注残高と、将来の旺盛な需要の両方によって支えられているのです。
(リスクを考える)石油需要減少が本銘柄に与える影響
三井海洋開発は海上油田の開発に携わる会社として石油需要減少の影響を受けやすい会社であることを理解する必要があります。
重要なのは、三井海洋開発の顧客(エクソンモービルやペトロブラスなど)は、「今日の石油価格」ではなく、「30年後の石油需要と価格の予測」に基づいて、新しいFPSOを発注するかどうかを決めている、という点です。
したがって、三井海洋開発の新規受注にとっての最大のリスクは、 「顧客である大手石油会社が、EVや再生可能エネルギーによる石油需要の減少が、自分たちの予想よりも『早く』来ると確信した時」 です。
リスクを分けて考える
反面、石油需要が減っても、売り上げは変動しにくいという強みの理解も重要です。
その理由は、現在稼働中の17隻のFPSOが生み出す「チャーター(賃貸・操業)売上」が、石油の「価格」や「生産量」に左右されない仕組みになっているからです。
・契約が「長期固定」である
FPSOの契約は、15年〜25年という超長期です。この期間中、三井海洋開発が受け取るチャーター料(家賃)は、基本的に固定されています。
・ 売上の基準が「稼働率」である(最重要)
顧客(石油会社)から支払われるチャーター料は、「今月どれだけ石油を生産したか」ではなく、「今月、FPSOが何%の時間、正常に稼働できる状態にあったか(稼働率)」に基づいて計算されます。
つまり、極端な話、石油会社側の都合で生産を一時的に止めたとしても、三井海洋開発のFPSOが「いつでも生産できますよ」という状態で待機さえしていれば、売上(チャーター料)は満額入ってくるのです。
石油需要の減少がビジネスに与える影響は、2つの部門で全く異なります。
- チャーター事業(現在の17隻)
- 影響: ほぼ無い。
- 理由:長期固定契約と稼働率ベースの報酬に守られており、非常に安定している。
- EPCI事業(将来の新規受注)
- 影響: 非常に大きい。
- 理由:将来の石油需要が減ると石油会社が判断すれば、新しい海洋油田の開発(=新しいFPSOの発注)が止まってしまい、将来の成長が失われる。
成長性について
これまで、三井海洋開発の「安定性」と「成長性」について解説してきました。これだけでも十分に魅力的な投資先ですが、私がこの銘柄に長期投資を決めた最大の理由は、市場がまだほとんど織り込んでいない、「将来性」にあります。
それは、「日本の国産レアアース開発」という国家プロジェクトの主役となる可能性です。
レアアースが重要になる理由
- 地政学リスクの切り札: 現在、日本はEVモーターや高性能磁石に不可欠な重希土類(ジスプロシウムなど)の多くを中国からの輸入に依存しています。これは、米中対立が激化する現代において、日本の経済安全保障上の最大のアキレス腱となっています。
- 国内での開発が急務: この状況を打開するため、政府は「脱・中国依存」を国家戦略として掲げ、日本の排他的経済水域(EEZ)内にある南鳥島沖の国産レアアース開発を急いでいます。
なぜ「三井海洋開発」が選ばれるのか?
このプロジェクトは、水深6,000mという超深海からレアアース泥を採掘するという、世界でも前例のない挑戦です。そして、この「海側」の採掘設備(FPSOの応用型)を開発・建造できる技術を持つ日本企業は、事実上、三井海洋開発(MODEC)以外に存在しません。
経済合理性だけでなく、国家の安全保障が絡むプロジェクトであるため、海外の競合他社ではなく、日本の技術を結集できる同社が中核となって受注する可能性は極めて高いと考えています。
- 売上規模: このプロジェクトの目標は、まず日本の年間輸入額(推定1,000億円〜1,500億円規模)を代替することです。これを実現するための採掘船・プラント設備の受注額は、数千億円規模になると推定されます。これは、同社が現在手掛ける海外向け大型FPSO1隻分に匹敵する巨大案件です。
- 開発予定: 政府は2026年から試掘を開始し、2028年度以降の商業化を目指しています。私たちが期待するニュースが出るのは、2026年後半〜2027年頃になるでしょう。
世界の深海資源ビジネスへの「鍵」
ここが最大のポイントです。もし三井海洋開発が、水深6,000mでの採掘という超難関プロジェクトを世界で初めて成功させた場合、同社は「世界で唯一、深海6,000m級の商業採掘ノウハウを持つ企業」となります。
この技術は、レアアース泥だけにしか使えないものではありません。
| 資源の種類 | 主な含有資源 | 主な埋蔵地域 | 水深 |
| マンガン団塊 | ニッケル、コバルト | 太平洋公海(CCZ) | 4,000〜6,000m |
| コバルト・クラスト | コバルト、白金 | 西太平洋の海底山 | 800〜2,400m |
| 海底熱水鉱床 | 銅、亜鉛、金、銀 | 沖縄トラフ、大西洋 | 1,000〜4,000m |
| レアアース泥 | 重希土類 | 日本の南鳥島EEZ | 5,000〜6,000m |
世界中の企業が狙っている「マンガン団塊」なども、同じ水深6,000m級に眠っています。
三井海洋開発が確立した技術(ノウハウ)は、これら世界のあらゆる深海資源開発プロジェクトに応用可能であり、同社が「深海開発プラットフォーム」のデファクトスタンダード(業界標準)を握る、計り知れないポテンシャルを秘めているのです。
この「石油の次」を見据えた壮大な将来性こそが、私が同社に長期投資する最大の理由です。
考えなければいけない採算性について
なぜ採算が合わないのか。理由は単純です。
- 莫大な初期投資と技術コスト: 私たちが分析した通り、水深6,000mから資源を引き揚げる技術はまだ確立されていません。その開発コスト、採掘船の建造コストは莫大です。
- 陸上との価格競争: 現時点では、中国が陸上で(環境コストを度外視して)安価に生産するレアアースや、インドネシアの陸上鉱山から採れるニッケルの方が、製造コストは遥かに安いです。
将来、採算が合うようになる「3つの理由」
理由①:「経済安全保障」という、価格を超えた採算性
これが最も重要な要因です。
- 日本のレアアース泥: これは純粋な経済活動ではなく、「国家安全保障プロジェクト」です。目的は「中国依存からの脱却」です。 もし中国が輸出を停止すれば、日本のハイテク産業が受ける損害は年間数兆円規模に上ります。そうなるリスクを防ぐために、たとえ陸上鉱山より2倍、3倍コストが高くても、国内で自給できる体制を「国策」として構築することには、計り知れない価値(採算性)があるのです。 国が補助金を出してでも、三井海洋開発のような企業に開発させる動機がここにあります。
理由②:陸上資源の「限界」
陸上の鉱山も、永遠に安価なわけではありません。
- 品位の低下: 採掘しやすい高品位な鉱床は減少し、だんだんと質の悪い鉱石しか採れなくなっています。
- 環境規制の強化: 陸上鉱山は、土壌汚染や放射性廃棄物(トリウムなど)の処理といった環境問題に直面しており、その対策コストは世界的に上昇しています。
- 地政学リスク: インドネシアのニッケル禁輸や、アフリカのコバルト鉱山での紛争など、陸上資源は政治的にも不安定です。
陸上のコストが上がり続ければ、いずれ深海採掘のコストと逆転する「Xデー」が訪れます。
理由③:爆発的な需要の増加
EV(電気自動車)、AIデータセンター、風力発電。これらの次世代産業は、すべて深海資源(ニッケル、コバルト、ジスプロシウムなど)を爆発的に消費します。
需要が供給を上回れば、金属の市場価格そのものが上昇します。価格が上がれば、現在は採算が合わない深海採掘でも、十分に利益が出るようになります。
結論
ここまで三井海洋開発(6269)の「安定性」「成長性」「将来性」を分析してきました。
この銘柄は、長期投資銘柄として適性がすごく高いと感じました。
「揺るぎない安定性と成長性」という土台
まず、安定性で分析した通り、17隻のFPSOが稼働するチャーター事業は、今後10年単位で見ても揺るぎない「安定性」を誇っています。これが、私たちの投資の強力な安全マージン(下支え)となります。
また成長性についても受託案件を抱えており、その1件1件が巨大化しており、成長を見込むこともできます。
「夢」を実現させる2つの採算性
「レアアース開発」は、現時点でコスト面だけを見れば採算が取れないかもしれません。しかし、このプロジェクトの採算性は、通常のビジネスとは異なる次元で考えるべきです。
- ① 経済安全保障としての採算性 中国がレアアースを「兵器化」するリスクが高まる中、日米両国にとって「脱・中国依存」は国家の最優先課題です。この開発の進捗速度は、時代のリーダーがどれだけ経済安全保障を重視するかで決まります。もし、トランプ氏や高市氏のような、自国の安全保障を最優先するリーダーシップが強まれば、このプロジェクトは国策として一気に加速(前倒し)すると私は考えています。 アメリカが、同盟国である日本からの安定供給にどれだけの「安全保障プレミアム」を支払うか。それこそが、この事業の本当の採算性です。
- ② 技術革新による将来の採算性 さらに長期的に見れば、「水深6,000mからの採掘」という技術革新(イノベーション)そのものが、将来の製造コストを劇的に下げ、商業ベースでも採算がとれるようになる可能性も十分にあります。
日本の「底力」への投資
最後に、少し個人的な話をさせてください。
日本が、自国の海に眠る資源で「資源大国」になれるかもしれない。これは、私にとって非常に喜ばしい、夢のあるストーリーです。
もちろん、水深6,000mという技術的な壁、採算性の壁など、課題は山積みです。
しかし、かつて世界をリードした海洋国家、そして近年まで世界一と謳われた技術国家であった日本の底力は、まだ失われていないと信じています。この壮大な国家プロジェクトの主役として、三井海洋開発がその底力を見せてくれることを、一人の日本人として、そして一人の投資家として、心から期待しています。
-
前の記事

【投資メモ】【2025年10月4週目】総資産300万から8,000万を目指す男の資産状況メモ 2025.10.25
-
次の記事

【投資メモ】【2025年11月1週目】総資産300万から8,000万を目指す男の資産状況メモ 2025.11.08